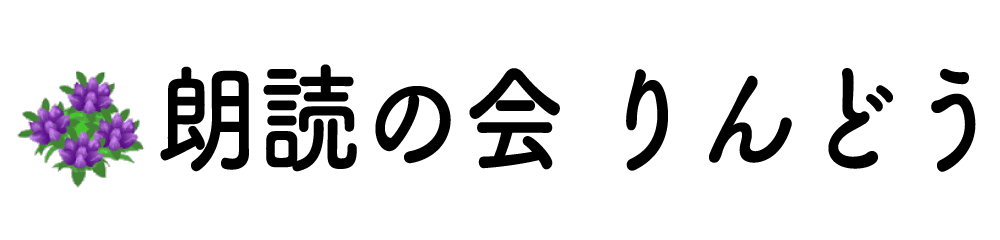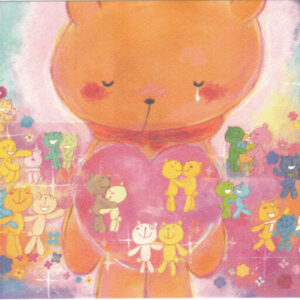川崎サマースクール(川崎市民プラザ)にて
「福島の子どもたちに会って」
7月31日から8月7日と、8月8日から12日までの2組に分かれて、
福島県の子どもたちが夏休みを過ごすために、川崎にやってきた。
地元での野外活動を制限されている子どもたちが一番喜んだのは、
やはりプレーパークでの泥んこ遊びと、プール。
思い切り好きなことをして遊んだ子どもたちは、みんな満面の笑顔だった。
りんどうの朗読は、ランチのあとの腹ごなしの時間だったから、
みんな本当は部屋でゴロゴロしていたかったのかもしれないけれど、
朗読会場まで出てきてくれた(みんな、ありがとう)。
最初は、何が始まるのかと構えているような子どもたちに、
「みんなにも参加してもらいます」と一役を振り、台詞の練習をした。
「行けっちゃ さやさや」という笹の葉っぱの音などを
子どもたちに担当してもらって、「なら梨とり」という民話を朗読した。
朗読を始めると、それまでそわそわしていた子たちもだんだん集中してきて、
話の山場では、みんなの意識がふっと集まったと感じられる場面があった。
これこそ演じる者が幸せを感じる瞬間だ。
子どもたちと一緒に一つの話を作り上げた、というと大げさかもしれないが、
とても嬉しい時間だった。
福島に帰る日、子どもたちはみんな、バスから身を乗り出すようにして手を振ってくれた。
私たちもバスが見えなくなるまで手を振って、別れを惜しんだ。
川崎での数日間が、あの子たちのいい思い出になるようにと、
私も川崎市民の会の皆さんもそう願っていた。
私は、サマースクール開校式での、リーダーの江田さんの「チェルノブイリの頃から危険は分かっていたのに、
こんな事になってしまって本当に申し訳なく思っている」という言葉に、何よりも共感する。
こんな理不尽な“今”を生きていかなければならない子どもたちに対して、
こんな“今”を作ってしまった私たち“おとな”は謝らなければいけない。
それは、積極的に原子力発電を推進したか否かにかかわらず、
こんな危険なものの存在を許してしまった“おとな”の責任なのだ。
「川崎の人には福島の人の気持ちは分からない」、「汚染地になんか誰も来ないよ」と、
たまたまそばにいた福島の小学4年生たちの声を耳にした。
私たち“おとな”のせいで、こんな思いを彼らにさせてしまっている。
“おとな”のせいで、こんな今を生きなければならない子どもたち。
しかも彼らはこんな今の、その先にある未来まで背負わされているのだ。
それでも私たちに向ける澄んだ瞳や、柔らかい頬、小さな手のぬくもりで、
私たちを癒し幸せにしてくれる子どもたち……。
彼らへの謝罪と感謝の気持ちを抱きながら、再び福島の子どもたちにまみえる時を待とうと思う。
2011.8.15 by K